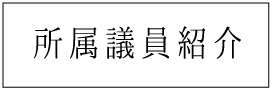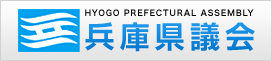石井 健一郎議員が一般質問を実施
質 問 日:令和2年12月8日(火)
質 問 者:石井 健一郎 議員
質問方式:分割方式
1 県職員の在宅勤務制度の取組について
国は、コロナの感染拡大を防止する観点から、多くの人が集まる場所での感染の危険性を減らすため、通勤ラッシュや人混みを回避し、在宅での勤務も可能となるテレワークを積極的に活用するよう呼びかけており、コロナ禍が続く中、残念ながら、従来は時間や場所を有効に活用した多様な働き方を実現するためのテレワークが想定していなかった形で急速に普及している感がある。そして、今後は新たな働き方のひとつとして定着していくのではないかと考える。
県においては、平成27年に中学校就学までの子を養育する職員のうち、本庁で勤務する職員を、また平成30年4月からは対象を全職員に試行的に拡大し、在宅勤務制度の実施を始めたところだが、新型コロナ感染症対策に係る緊急事態宣言が発令され、対策業務に従事する職員を除き、在宅勤務により出勤者の原則7割削減に取り組んだところである。
テレワークの問題点として職員同士のコミュニケーションの取りにくさや私生活と仕事の切り替えの難しさ等が挙げられる。こういったことは時間外労働の把握があいまいになることにもなりかねない。テレワークであっても時間外労働は労働基準法で規制されており、地方自治体も法の趣旨を踏まえた対応が求められている。労働基準法では事業場外みなし労働時間制等を認めているが、本来は外勤の営業マン等、上司による労働時間の把握が難しい職種を念頭に設けられた制度である。県では、在宅勤務をする職員の勤務時間の把握等の労務管理をどのようにしているのか。また、電話をかけるとその職員は在宅勤務で今日はいません、というようなこともあったが、県民からの問い合わせに対応できるような、在宅勤務時の業務の進め方が求められているのではないか。
そこで、これからも在宅勤務という働き方は継続されると思われるが、緊急事態宣言期間中における在宅勤務の取組を踏まえた上で、今後どのように進めていくのか、当局の所見を伺う。
2 会計年度任用職員制度の導入後の運用について
厳しい地方財政の状況が継続する中、教育や子育てなど増大、また多様化する行政サービスの重要な担い手であった地方自治体における臨時・非常勤職員数は平成17年には約45万人だったが、平成28年には約64万人と増加していた。
また、地方公務員の一般職の非常勤職員の任用等に関する制度が不明確であるといった指摘もあり、様々な制度上の課題が挙げられていた。
そのような中で、地方公務員法と地方自治法の改正を受け、本年4月から、地方自治体で働く臨時・非常勤職員は会計年度任用職員へ移行し、一般職と同様に守秘義務や政治的行為の制限を課す一方で、期末手当の支給や職務の内容と責任、職務経験等に応じた給与決定、フルタイムの場合、退職金支払いの対象になるともしている。近年多様化する行政需要に対応する多くの臨時、非常勤職員全体の適正な任用・勤務条件の確保が会計年度任用職員制度の目的であるが、自治体にとっては人件費増加も懸念されることから、国は、会計年度任用職員制度への移行に伴い、財政上の制約を理由として、職の必要性を検討することなく職員を意図的に減らすこと、期末手当を支給する一方で給料を減額すること、フルタイムで任用していた職員の勤務時間をわずかに減らすことでパートタイムにすることは、法の趣旨から適切ではないと指摘している。
そこで、県として会計年度任用職員制度を導入した結果、適正な任用・勤務条件の確保といった、法の趣旨に合致する運用が出来ているのか、また、就労意欲の向上につながっているのか、当局の所見を伺う。
3 就職内定率急落に係る県の支援について
来春卒業予定で就職を希望する大学生等の就職の内定状況について文科省・厚労省が行った調査によると、大学生の就職内定率は前年度と比較し7ポイント減少し、7割を切った。これはリーマンショック以来の下落率であり、コロナ禍の影響が明らかになった。短大や専修学校も13~15ポイントと過去最大の落ち込みとなっている。ちなみに、大学生の地域別の就職内定率は関東地区が最も高く、74.4%であり、近畿地区は71.5%であった。
業界によっては、新型コロナウイルスの収束の見通しが不確実なため、採用人数の抑制や内定取り消し、さらには来年度の選考活動を行わないという動きも出ているという報道もある。国においては雇用状況の悪化を受けて、第2の就職氷河期をつくらないとし、卒業後3年以内の既卒者は新卒者扱いとするよう改めて経済団体に要請する等の対応をしているが、現在のコロナ禍の終息は見通せず今後とも厳しい状況が続くことも考えられる。
また、学生側も最近の売り手市場から一転したことや、コロナの影響で就職イベントの中止や大学構内の閉鎖によるオンライン授業の増加をはじめ、情報の共有が難しくなっている。さらにはオンラインによる説明会や面接を導入する企業も増加するなど就職活動の状況の変化もあり、困惑しているのではないかと思う。
コロナ禍で1月~9月の転出超過が全国で最悪となっている本県にとっては、新卒者の県内就職や県外からのUJIターン希望者の就職促進はもとより、東京や大阪への本県からの人口流出の他、四国や中国地方等、これまで本県に移住してきた層がコロナ禍で減っているという新しい課題もあると指摘されている。
そこで、県として市町とも連携し、県内の求人情報を積極的に把握し、学生と企業のマッチング支援を強化する必要があると考えるが、当局の所見を伺う。
4 航空機産業の今後の見通しと県の支援について
新型コロナウイルスの世界的流行により、航空業界は危機に瀕している。各国の出入国制限や空輸需要の縮小によって路線の運休、大幅減便を余儀なくされている。この世界的な航空機需要の消滅で航空機産業は全国的に大きなダメージを受けている。三菱重工では最盛期にはボーイング社から777と787で約270機分の機体部品を納入していたが、ボーイング社自体が2021年には年間で100機弱の生産まで引き下げる予定である。この影響は三菱重工に限らず、日本の航空機産業全体に及ぶことになる。県内にはボーイング787の機体部品を担当する川崎重工や新明和工業をはじめとする多くの航空機関連企業がある。航空機の部品数は自動車と比較しても大変多く、また、専門性も高い。特に、他の産業に切り替えにくい機体部分を担当する中小企業には相当な影響があると思われる。
この問題は早期に市場が回復する見通しが立っておらず、IATA(国際航空運送協会)では、今年は世界全体の航空需要で昨年比66%減少、来年はコロナ禍前の74%水準、2023年からようやく回復し始め、本格復帰は2024年という見通しを立てており、この3年間は厳しい状況が続く。
航空機産業に関しては、県としても世界的な需要拡大を踏まえ、成長が期待される産業部門の一つとして、様々なセミナー開催や国内で初めての航空産業非破壊検査トレーニングセンターを設置し人材の養成をする等積極的に取り組んできたところである。
この危機を乗り越えることにより好機が訪れる可能性が今後十分に期待される。コロナショックは短期間であれば資金繰り融資等で乗り切れることもあるが、長期間に亘ると、資金繰り融資は赤字補填に過ぎなくなる。もともと航空機産業はスパンの長い産業であり、10年、20年先を見据えて事業展開する必要がある。
そこで、ものづくり県・兵庫の一翼を支える、また、先導するポテンシャルのある県内の航空機産業に対する、県としての現状認識と今後の取組について、当局の所見を伺う。
5 県営住宅の共益費の徴収について
民間の賃貸住宅では、共用部分の電気代、水道代等の共益費は家賃とあわせ管理会社や不動産業者が徴収しているところが多い。一方、県営住宅では、家賃は県または指定管理業者が徴収し、共益費は自治会が徴収しているが、その徴収に苦慮している自治会もあると聞いている。
昨今、都市部のマンション等の集合住宅では、住民の高齢化、共働き家庭や独り暮らし世帯の増加に伴い、人間関係が希薄化し、隣戸の付き合いもあまりないというところも多くなり、今後もその傾向が強くなるであろうと想定されている。このことは、県営住宅も例外ではなく、2020年4月現在の入居戸数39,312戸のうち、世帯主が65歳以上の世帯数は23,560戸で59.9%となっている。また、高齢単身世帯は13,579戸で高齢世帯の56.7%を占めるなど、住民の高齢化は年々進んでいる。また、公営住宅には、市場で適切な住まいを確保することが困難な世帯に、安心して暮らせる住生活の場を提供するセーフティーネットとしての役割もあることから、その供給目的から考えるとその傾向が一般集合住宅よりも顕著に出てくることが考えられる。
公営住宅の管理問題については様々な課題があるが、まずは、自治会による共益費の徴収が困難になるケースも出てくることが懸念される。共益費の未納は徴収を担当する人にとって大きな負担であり、住民間のトラブルの要因となり、コミュニティの維持に大きな支障をきたす場合もあると認識している。
そこで、自治会による共益費の徴収については、県や指定管理者がアドバイスを行っていると伺っているところであるが、県においても、コミュニティの維持に支障をきたす県営住宅が出てくる前に、県による家賃と共益費の一体的な徴収について、早急に実施するべきではないかと考えるが、当局の所見を伺う。
6 「魔の7歳」対策の推進について
我が国の交通事故死は歩行中や自転車利用中が欧米の2.5倍以上多いとされている。その中でも小学校1、2年生にあたる7歳の交通死傷者が交通事故死者数の最も多かった時と比較し減少しているとはいえ依然として多く、魔の7歳という言葉がある。
就学前は、幼稚園や保育所への送り迎えなど大人と一緒に行動することが多い子ども達が、小学生になると、子ども達だけで登下校や遊びに出かける機会が増える。そして、親から離れ、自分の足で街中に出た子ども達が、本来、子ども達を守るはずの大人によって、交通事故の犠牲になってしまっているのである。
その多くは身近な生活道路等で犠牲になることが多い。理由として都市部の住宅地では、狭い道路が多く、見通しが悪い上、住宅地内の道路が抜け道となっていることや、車と歩行者が分離できていないことが挙げられる。警察ではゾーン30等の取組を進めてある程度の効果を上げているようだが、通学時の近隣住民の交通整理等の協力がなければ、実際に速度を下げさせることはおぼつかない。狭い道路では警察の取り締まりもなかなか難しいと思われるが、ハンプ等の物理的なハード面対策は住民の理解を得にくいようで難航しているようだ。
しかしながら、悲惨な交通事故を減らすためには、このハード面対策について、その目的や効果を地域の住民によく説明し、理解を得ることへの努力が大切だと考える。近隣住民が活発に活動している地域では協力を得やすいということも考えられる。小学生については特に登下校の時間帯に注視する必要があるが下校時間は、分散下校となることから、見守り等に協力していただくことも困難と聞く。
大切なのは人の命を守ることであり、今までも取組を続けて頂いていることに感謝するとともに、ハード対策を含めた生活道路対策を更に推進するため、警察が、行政・地域としっかりと連携をとって悲惨な交通事故死をなくすことに努めるべきと考えるが、当局の所見を伺う。